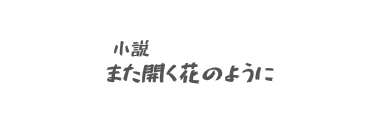今から24年ほどまえ、自分が体験した強迫性障害(強迫神経症)について知ってもらいたくて書いた文章です。
時代とともに変化していることもありますし、手を加えたい箇所もありますが、文章はそのまま、見出しをつけ三つの記事を一つにまとめました。
強迫性障害という病がどんなものか知らない人も多いということをすっかりわすれていました。
症状や程度は人それぞでしょうが、ここでは、
(1)「手をあらうのが止められない 強迫性障害」(ジュディス・ラパポート著 晶文社刊)
(2)「すべてのものは、あるべきところに」(マーク・サマーズ著 青山出版社刊)
を参考に、私の場合を例にあげて説明したいと思います。
主な症状である強迫観念と強迫行為・私の場合
最初の症状といえるのは、私の場合、目に見えない刺(とげ)でした。
指の先が少しでもザラリとかチクリといった感覚を捉えてしまうと、それが、人の命さえをも奪いかねない恐ろしい刺のように思えてしまうのです。
「自分が、誰かを傷つけてしまうのではないか、あるいは、殺してしまうのではないか」といった強迫観念は、日に日に強くなり、ありとあらゆるところに現われる刺を振り払うのに、私は、必死でした。
普段私たちは、自分の行動は自分でコントロールできるものだと思っていますから、望んでもいないことをしてしまうのではないかと怯えるのが、いかに理不尽かは本人もわかるのです。しかし、病における強迫観念は、とても圧倒的でリアルなものです。
アメリカの精神科医、ブライアン・L・ワイス氏が書いた「前世療法」(PHP研究所)という本を読んで、ぜひ自分も受けてみたいと思った患者さんは多いと思いますが、いくつもの生を繰り返してきた魂に刻み込まれたトラウマのせいとでもいわれないかぎり納得できないほどのものなのです。
私も、とげばかりではなく、洗った手から床にこぼれたかもしれない水滴のせいで、だれかが滑って頭を強く打って死んでしまうのではないかと怯え、駅のホームでは、人を線路に突き飛ばしはしないかと、脂汗をかいた手で鉄柵を握りしめていたものです。
汚れが取れない気がして手洗いを繰り返す、火の元の確認を繰り返すといった少しは知られた強迫行為もしっかりとありましたし、日々、病のためについやしたエネルギーたるや凄まじいものでした。
「ねばならない」という思いが強い性格で、バレーボールの部活を休むことなど考えられず、学校には通い続けていましたが、家から出れなくなる人がいるのも充分うなずけるほど、深刻な病です。
強迫性障害、あまり知られていないのは
参考書(2)には、
「強迫神経症は世界中で見られる病気で、たいていは発症率も人口のニ、三パーセントと、アメリカの場合と変わらない。(P.72)」と書かれています。
この病は、けして珍しいものではないようです。
では、なぜあまり知られていないのかといえば、おそらく、気が狂っていると思われるのがいやで、患者本人が、ひたかくしにするからなのでしょう。
「強迫性障害の場合は、成人患者の50パーセントが、子供のころにすでに想念(強迫観念)や儀式(強迫行動)につきまとわれていた。(P.20 -21 )」と、参考書(1)に書かれていますが、病を発症した子供たちの多くは、自分が狂ってしまったという恐怖を抱くとともに、誰にも気づかれてはいけないという孤独を背負い込んでしまうのです。
そして皮肉なことに、彼らが、親の強迫性障害を知らないというケースも、あるのではないでしょうか。
「強迫性障害は脳の病気である」
参考書(2)に「1986年に、アナフラニールという薬が強迫性障害について及ぼす影響についての研究が行われた。アナフラニールは脳内のセロトニン神経系に働きかけるのだが、アナフラニールを使った治療に70パーセントの被験者が反応した。これは劇的な一大発見だった。強迫神経症が治療可能な病気であることに、医師たちは初めて気づいたのである。(P.74-75)」と、書かれています。
実験は、全米で行われており、日本における強迫性障害の治療法が、いつ頃から変わったかはわかりません。
でも、何はともあれ、このように、幼児期のトイレのしつけの失敗などを原因とするフロイトの説が否定されたことは、患者が、正しい治療を受けられる可能性が生まれたということですからもちろん嬉しいことです。
しかし、5年前に、参考書(1)で、「強迫性障害は脳の病気である」という章見出しを目にしたときの私は、いよいよわかってしまったかと複雑な思いを抱いたものです。
患者本人は、自分におきていることがもはや心配性とか神経質といった言葉ではすまされないとわかってしまうのですから、私にしても、どこかでは、頭・脳がおかしくなってしまったと思っていたのでしょう。
でも、それを認めたくはありませんでした。
脳の病と聞いて、他の肉体的な病と全く違う印象を受ける人は多いはずです。
幸い(?)、小学校の高学年で診てもらった医者も
「スポーツでもすれば気にならなくなるでしょう」と言ってくれたし、器質的な病気ではなく、精神的なことが原因なのだいう説にしがみついていたかったのです。
それでも、私の場合、強い不安感は残っていましたが、激しかった強迫性障害の症状はほとんど消えた時点で、脳の病という説を耳にしましたから、ある程度の余裕がありました。
けれども、、中学・高校の頃は思考に柔軟性がなかったうえに、他の人に頭がおかしくなったと思われることをとても嫌っていましたから、もし、医者に「脳のバランスがくずれているから薬を飲みましょう」などと言われていたらどれほど傷ついたかわかりません。
特に子供の患者に対しては、大人たちの気配りがとても大切なように思います。