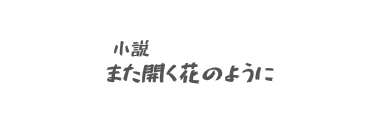良い子でありたい私と

確かに染野美術館は小さな美術館だが、その敷地は以前、我が家が建っていた場所のみにおさまっているわけではなく、かつて友ちゃんの家があった土地にまたがっている。
つまり友ちゃんの家、染野家と私たち山瀬家は隣同士だったのだ。
兄は三つ、友ちゃんは私の二つ上。
両親ともに仲が良かったこともあって、私達三人は本当の兄弟のように育った。
そう、三歳の私の手を引いて幼稚園に一緒に通ってくれたのも、泣いてはいないかと教室をのぞいては声をかけてくれたのも友ちゃんだった。
昭和四十年代の典型的な日本の家庭、そんな我が家とは違って、お洒落で綺麗なお母さんが焼くクッキーやケーキの甘い匂いが満ちていた友ちゃんの家は、今も時々、私の夢に出てくる。
窓から差し込む光が白い壁と飾られた季節の花々を照らしていた玄関。いつの間にか眠ってしまったこともあるフカフカのソファーが置かれたリビング。その大きな窓から見える、木々と、おじさんがアトリエとして使っていた離れ。我が家にはまだなかったベッドの置かれた友ちゃんの部屋。
いろんなことがあって忘れていた時期も長かったが、友ちゃんと彼女の両親のおかげで、私の子供時代はとても豊かだった。二家族合同でお花見をしたり、花火をしたり。夏休みには、電車に乗って互いの田舎に泊りにもいった。
日々の遊びも友ちゃんがいるといないじゃ大違い。
彼女の家の庭で花の精があらわれるのを待ったり、我が家の物置の引き戸を別世界の入り口に見立て様々な場所と時代を旅したり。彼女がいると私たちは完璧に夢の世界で遊ぶことができた。
背は普通。やせていて髪はポニーテールにしていることが多くて目が少し上がっているのが特徴。
あるフィギャースケーターのまだあどけなさの残る幼い日の映像が流れたとき友ちゃんに似ていると思ったが、そう感じるのは私だけかもしれないから彼女の名前を出すのはやめておこう。
勉強が特別できたわけではないように運動会で大活躍していた記憶もないが、友ちゃんはとにかく身軽で、自分の部屋の窓から一階の屋根に降り、さらに我が家との境にある塀の上に飛び移ることなどはお茶の子さいさい。思い出すとぞっとするが、下を車がビュービューと走る橋の欄干にのぼり、両手を広げて歩くことさえあった。
木をよじ登りどうにかこうにか塀の上に足をおろし恐る恐る立ち上がったとたんに下まで落ち、頭を打って病院に運ばれてしまうような私とは大違い。
友ちゃんと兄に置いてきぼりをくらい、べそをかくこともしょっちゅう。ふたりともいじわるをするつもりなどはなかったのだろうが、悲しくてみじめな思いをするたびに、同性で隣の家の子である友ちゃんに対して嫉妬と恨みが募っていってしまうのは仕方ないこと。
おまけに、彼等と同じ公立の小学校に通いはじめたときには、すでに極端なまでに頭が固く、良い子になってほめられたいし、規則をやぶるなんて絶対にできなかった私からすれば、彼女の行動は良い子と思えぬことがしばしばだった。
「俊ちゃん、綾ちゃん」今も時々、その元気な声を思い出すが、私が一年生になると彼女は毎日のように我が家に声をかけてくれて、兄よりも一生懸命に学校への道を教えてくれた。「綾ちゃん、横断歩道じゃなくてこの歩道橋を渡るんだよ」「線路の下をくぐったら二つ目の角を左。学校で決められた道を歩かなきゃ駄目だよ。ひとりになったらあぶないからね」
ところがだ。数週間もするとそんな彼女が、「ねぇ、タローにあいさつしていこうよ」「つつじの公園を突っ切っていこうよ」と、言いはじめたのだ。
友ちゃんの提案に「うん」とうなずく兄の目はきらきらと輝き罪の意識などはほんの少しも感じていない様子。私が期待するように「友ちゃん駄目だよ」と、きっぱり断ってくれることなど一度もなかった。
母からも教わった大きな道をわき目もふらずに歩いていきたい私が、「寄り道はいけないんだよ」と叫んでも、「大丈夫だよ」と、細い道をどんどん先に進んでいってしまうふたり。「お兄ちゃんや友ちゃんと一緒に学校まで行くのよ。ひとりになっちゃ駄目よ」と、言いきかされていた新入生の私は、彼等とわかれることもできず怯えながら後をついていくだけ。
無愛想な犬のタローが大きな口をあけてあくびをしようが、マジェンタ色のつつじが満開になろうが私にはどうでもよかった。ただ、誰かにみつかり叱られることなく早く学校に着きたいだけだった。
音楽室に移動する途中で、廊下に立たされた友ちゃんの姿を見てしまったのも、まだ一年生のときだったように思う。後できいた話によれば授業中ちょっかいをだしてきた男の子をぶちかえし喧嘩になったらしいが、あのとき、当の本人、友ちゃんは一緒に立たされた男の子と小声で話しながら笑みさえ浮かべていた。しかし、それに反して私の受けた衝撃は大きかった。まるで、重罪を犯し警察に連行される彼女の姿を目にしてしまったように震えあがり、あわてて視線をそらしていた。
それほど友ちゃんと私は違っていたわけで、四十半ばの今では、もし、本当に来世というものがあるなら今度は彼女のような子供に生まれてきたいと心から思う。
けれど、自分がしてはいけないと固く信じていることを平気でやってしまう彼女を、あの頃の私に、彼女は彼女だから受け入れなさいと言ってもそれは無理な話。兄が大好きな友ちゃんに対する私の不満はますます強くなっていった。
父をがっかりさせてまでおじさんの絵画教室をひとり抜けてしまったのも、彼らに対するささやかな抵抗、自分は兄や友ちゃんと違うのだと思いたいゆえだったのかもしれない。
友ちゃんのお父さん、染野豊氏は東京藝術大学を卒業した油絵画家。特定の団体には属していなかったが、受賞者にはそうそうたる名が並ぶ今はもう終了してしまった有名な賞も受賞している。まぁ、隣人でなくとも彼の名を知っていたかときかれれば返事に困ってしまうが、現在も彼の絵を愛する人が多いことは確かだし、素朴な色と形の中に宿っている確かな力が、みる人をねぎらい元気付けてくれる彼の絵が私も大好きだ。
当人が描く絵はお世辞にも上手とはいえなかったが、賞をとる前からおじさんの絵にほれ込んでいたという父は見る目だけは持っていたのだとつくづく思う。
おじさんも先生ぶったところのまるでない優しい人で、私たち子供の絵画教室を始めるまえから、自分の家のアトリエで月数回、私の父を含めた数人に絵を教えてもいた。父が言い出しっぺだったのか、生徒は皆、中年の男性で、教室の後はほとんど毎回飲み会になり、私も、何度か母の作ったつまみを届けにいった。あの時見た父の楽しそうな赤ら顔といったら。そんな席で「先生、うちの俊や綾にも絵を教えてやってもらえませんか」と頼んだのだろうか。
私が兄と一緒におじさんのアトリエに通いはじめたのはまだ幼稚園のとき。曜日が決まっていたのか不定期だったのかはっきり覚えていないが、毎回アトリエには、兄と私と友ちゃんの他に十人ぐらいの子供が集まってきて、みんなで公園まで写生をしにいったり、おばさんが焼いてくれたケーキを食べたり、遊びの延長みたいに自由で楽しい教室だった。
何より私にとっては、おじさんと教室を手伝っていたおばさんが、「ああ、面白い絵だね、綾ちゃん」「綾ちゃんの絵、動きがあっていいわね」などとほめてくれることがうれしくてたまらなかった。口先だけのお世辞でないことは彼らの表情や声から伝わってきた。
しかし、口惜しいことに、それは私に対してだけではなかった。兄の絵をのぞきこみおじさんがうれしそうにうなずいたのも、友ちゃんの絵を見ておばさんが静かにほほえんでいたのも私は見ていた。
兄の絵はともかく、不思議な色使いの友ちゃんの絵は、画面の外へと広がっていくようなのびやかさがあり、自分の絵が一番と思いたい私もどきりとさせられることがあった。
三年生になって間もなく、バレエを習いはじめるからといってひとり教室をぬけてしまったのも、作品展を開くとダントツで大人たちの注目を集めてしまう彼女に対するやっかみがあったような気がする。
「習い事は絵かバレエのどちらかひとつにしなさい」友達の発表会にいき自分も彼女のようにきれいな衣装を着てスポットライトをあびたいと思ってしまった私に、確かに母はそう言った。
でもそれは、けしてむくとは思えぬバレエをあきらめさせたかったから。
その証拠に、私が早々と絵画教室の仲間のまえでやめると公言してしまうと、あわてて父と一緒に「バレエも絵も両方習えばいい」と引きとめてくれた。けれど私は突っぱねた。
おじさん、おばさんに「残念だ」「さびしい」と言われながらひとり教室をぬけていく。兄や友ちゃんに差をつけ自分だけ特別になれたようで格好いいと思った。
あの頃から私は、ひとり黙々と画用紙やカンバスに向かうなどという地味なことより舞台やスポーツのコートに立ちみんなの注目を集めたいと思うようになっていたのだ。
しかし、とにもかくにも、バレエはすぐにあきてしまったようだ。家で練習するなんていうことは全くなく、前回習った踊りをすべて忘れてレッスンに出かけていく有様。当然、先生には叱られるし発表会前にはひとり居残り練習をさせられた。
もちろん行くのが億劫になっても、私にはバレエがあるから絵には関心がないというふりをしつづけるしかなかったわけだが、兄はといえば、私がやめても、中学生になっても、嬉々として絵画教室に出かけていった。
ひとり残された茶の間の窓からは塀をはさんで友ちゃんの家が見え、その向こうには、彼が「こんにちは」と入っていっただろう木造のアトリエが建っている。風に乗り、油絵の具のにおいとともに、今にも友ちゃんの甲高い笑い声が聞こえてきそうな気がして開け放した窓をわざわざ閉めたことさえあった。
ひとりでライバル心を燃やしていた相手、友ちゃん。しかし、それじゃあ、彼女が本当の敵だったかといえば、けして、そんなことはなかった。
カトリックの幼稚園に通っていたころの私は、家で折りたたんだ布団を重ね練習した飛び箱のように、最初は出来なくても努力すれば何でもできると信じていたし、好きなことは夢中になるくせに他のことは今ひとつで宿題をやりながらよく母に怒られていた兄と違って自分は優秀な子だと思っていた。
けれど、期待で胸をふくらませ通いはじめた小学校は幼稚園と違っていて、集団行動にすんなりとついていけない自分というものが浮き彫りになってしまった。入学式から数日後の健康診断で身支度をして廊下に並ぶまでにもたつき、担任に「さっさとしなさい」と、後頭部を小突かれたのが最初だろうか。私には、先生の指示を一瞬にして理解しすばやく行動するということが難しく、えらく緊張しながらどうにかこうにか皆についていくというのが常となった。
しかし、教員歴の長かった担任だって、この子はぼーっ、としていて私のいうことをろくに聞いていなかったと思い頭を小突いたのだ。子供の私が、ああ自分は指示を受けてから行動にうつすまでに時間がかかるのだな、などと静かに受けとめられるわけがない。親の自慢であるはずの自分が他人より劣っているなんて絶対に認められない。
自尊心の傷つくことがあればあるほど、私は猛烈にまじめな良い子を先生にアピールした。
恐い担任だったが良い子は大好きで、努力のかいあって「山瀬さんを見習いなさい」と、ほめられたことも何度かあった。
私にとって大人のいうことは絶対だったが、彼らを冷静に見られる同級生には、不快というより滑稽だったのかもしれない。何はともあれ、友だちから露骨ないじめを受けなかったのだけは幸いだった。
けれど、小学校といえば、コンクリートの四角い校舎に暗い空からしとしとと雨が降っている、そんな光景が浮かんでくるように、先生からねちねち叱られるものだから忘れ物に気づいてこの世の終わりのような憂鬱な気分になったり、言い出せず授業中におもらしをしてしまったり、幼稚園で仲の良かった子供たちが他の小学校にいってしまったため友だち作りに苦労したりと、私にとってけして楽しい場所ではなかった。
だが、小学生だった自分を振り返るとき、きらきらした思い出が先に浮かぶものだから、あの頃はまだ幸せだったとなるのだが、笑っている私のそばには兄と一緒にいつも友ちゃんがいた。
私がそうだったように精神的な問題は家族であってもかくしたいと思うもの。だから、あくまで推測だし具体的なことはわからないのだが、私の母は、例えば強すぎる不安感だとか、やや病的なこだわりだとか何かしらの生きづらさを抱えていたように思う。
知人の紹介で父と結婚する三十ちかくまで働くことなく家事手伝いをしていたし、何でも一生懸命だったから、食卓にはいつもたくさんの皿が並んでいた。おまけに、私ばかりか兄にまで布や毛糸を使って人形を作ってくれた。
しかし、それらは努力の賜物で、器用ではないぶん、他の人より多くの時間とエネルギーを注いで私たちを育ててくれたに違いない。
だから、兄と同じく私も母に感謝しているのだが、彼女には、子供が体験していることを聞かずとも正確に察してしまうほどの心のゆとりはなかった。
また、人嫌いというわけではなかったが、自分から積極的に関係を作っていく余力も、特に私たちが小さかったときはなかったように思う。
したがって、そんな彼女のことを理解し、フォローできることは何気なくフォローしてしまえるほど器の大きい友ちゃんのお母さんは、あの頃の母の、唯一の親友だった。
そして、おじさんにほれ込んでいた父はみんなでワイワイさわぐのが大好きだったのだから、私が絵画教室をやめようが、友ちゃんにマイナスの感情を抱こうが、夏休みがくれば二家族合同で互いの田舎に泊まりにいったり、プールにいったり、花火をしたり、冬休みになればクリスマス会をしたり、時にスキーにいったりといったことは少しも変わらなかった。
そして、そういった行事に参加するのもいやなほど私が友ちゃんを嫌っていたかといえばそんなことはなく、特に旅行の前の日などはうれしくてうれしくて眠れないほどだった。
どういう事情だったかもう覚えていないが、小学校三年生のとき、母と祖母と母の妹である里子叔母さんと私、四人だけで北海道を旅したことがあったが、あの時私は、生まれてはじめて、そしてその後も経験したことがないほどのホームシックというものにおちいった。
母も祖母も叔母も元気づけようといろいろな所へ連れていこうとするのだが、どこへも行きたくないし何をしても楽しくない。さびしいとか悲しいとか言葉にできるときはまだましと思えてしまうほど、沈み込み、気力が失せ、感情の鈍ったあの状態は今思いだしても恐ろしい。
あまりにも暗くてよくあそこから脱出できたとさえ思えてしまうのだが、光がさしてきた最初の場面として記憶に残っているのは、旅からもどりお土産を届けに友ちゃんの家にいったときのこと。
「途中で壊しちゃうからやめなさい」と母がとめるのもきかず買ったガラスの風鈴。毎日大切に持ち運んだそのお土産に友ちゃんは目を輝かせてくれた。
「きれいな色!」
「ねぁ、鳴らしてみて」
「うん」
チリン、チリン
「わぁー、すてき! 妖精みたい」
「でしょう? 私も妖精みたいだと思って買ったんだ」
今思えば、風鈴を持った妖精なんておかしいのだが、そんな会話を交わしながら、笑い喜ぶ力がもどってくるのを感じたものだった。
今も認めるのは少し悔しいが、ねたんだりうらんだりしていた友ちゃんに、実は大いに助けられていたのだ。