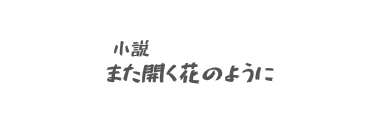おかしいとわかっているのに

きっかけとなるような出来事があったわけではない。
何も考えず繰りかえしていた朝の身支度、それが、どのような過程を経て、あんなふうに神経をすり減らす作業へと変わってしまったのか自分でもよくわからない。
ともかく、記憶に残っている時点ではもうすでに、神経の集中した指先が、シャツやブラウスやスカートや靴下、すべての衣類に触れるたびに、ザラリだとかチクリだとかいう不快な感覚をとらえ、頭はそれを、目に見えぬほどの小さな棘と認識するようになっていた。
実際には、毛玉や布の織り目に荒れた指先、あるいは指紋がひっかかり生じたわずかな感触が誇大に伝わってしまうだけなのだから、振り払おうとしても振り払うことのできない棘。
それでも私はそれをとるためすべての衣類をはたはたと振ってからでないと身につけることができなくなっていた。
強迫行為を繰りかえす人の中でもいろいろなのだろうが、私の場合、その棘で自分が傷つくことは少しも恐くなかった。ただ、それによって誰かを傷つけてしまうことが恐くて恐くてたまらなかった。
チクリとした感触を指先がとらえてしまったことでそこにあると気づいていながら取れずに放置したスカートの棘。
それが、例えば音楽教室の椅子の上に落ち後から座った人のお尻にささり血管をめぐり最終的には心臓に突き刺さり自分は殺人者となってしまう。
ありえないこと。けれど、その妄想を振り払えないほど、いつの間にか、私の頭の中で、不安や恐れがふくれあがっていた。
どれほどの時間をかけ症状が広がっていったかはっきりしないが、やがて手洗いも火の元の点検も命がけの作業となった。
手についているばい菌は人の命を奪う猛毒。火の元の点検に失敗すれば家族ばかりか、ご近所さんをも焼死させることとなる。
強すぎる恐怖のせいだろうか、ガスコンロの火が消えているかどうかなんてぱっと見ればぱっとわかるはずなのに、いくら顔を近づけ点火つまみをながめても、たてになっているという確信が全然持てない。
それで指先に力を入れて「開」の文字と反対側にねじってみる。(動かない。大丈夫)そう自分に言いきかせて手を放す。でも、その瞬間に反動で反対に回ってしまったような気がして同じ動作を延々と繰りかえすことになる。
六年生のとき母に連れられていった総合病院では「スポーツでもすれば気にならなくなるでしょう」と、言われただけ。
強迫神経症から強迫性障害と診断名が変わったのは、一九〇〇年代の半ばらしい。
そして、それが幼児期に受けたショックや過度のストレスにより精神的なバランスがくずれた結果起こるものではなく、脳内の神経伝達物質と関係のある内科的な病、つまりは脳の病気なのだと書かれた本を私がはじめて読んだのは三十歳を過ぎてからのこと。
一九七〇年代なかばに医者が何もしてくれなかったからといって責める気にはなれない。
いや、むしろ、あの時、彼がああ言ってくれたことに感謝さえしている。
棘が気になり衣類を振りつづけているときも、猛毒をとろうと手を洗いつづけているときも、私は、百パーセント、それがあると思い込んでいたわけではなかった。
常に、正常な自分が、妄想を振り払うことも、奇行をやめることもできない自分に失望し苛立っていた。
そう、私は、自分の頭がおかしくなってしまったことを誰よりもよくわかっていた。けれど、その事実はあまりにも恐ろしく、あの時点で受け入れるのは不可能にちかいことだった。
「やーい、気違いー!」はやしたてる七、八人の男の子たち。そして、派手なスカーフを頭にかぶり汚れた服を重ね着し、顔をしかめぶつぶつ言いつづけるひとりの女性。そんな光景から幼い日に受けた衝撃も関係しているのだろうか。
たとえ子供であっても、私は、頭の病を身体の病と同じようにとらえてはいなかった。
絶望的で、恥ずかしくて、恐ろしい頭の病。
もし、あの時医者が、「脳内のバランスがくずれていますから薬を出しておきますね」なんて言っていたとしたら、私は、口がきけなくなるぐらい打ちのめされたにちがいない。
しかし、幸いにして、彼は、あなたは治療の必要な病気なんかじゃないと保証してくれたのだ。
たとえ本能的には、スポーツでもすれば気にならなくなる、そんなあまいものじゃないとわかっていたとしても、そのおかげで、自分はどこもおかしくないと思いつづけることを許されたのだ。
かなり無理はあった。
棘がおちていないか心配で座っていた椅子をなでまわさずにいられない。
誰かがすべって頭を打つと大変だから、手を洗ったあとで水滴を床におとさなかったか確認せずにいられない。
そんな行為を誰かに見られて何をしているのときかれても、ちょっと精神的にバランスくずしちゃってと胸をはりこたえられる……そんな自信なんて少しもなかった。
誰だって理由をきいたら頭がおかしいと思うにちがいない。
だから、私は、家族にさえ、できるかぎり奇妙な行動をかくそうとした。
それでも、ついつい気を許してしまうこともあって、高校のとき、「やーい、精神病」と友だちからからかわれたことがあった。
でも、私にはへらへらと笑い返すだけの余裕があった。自分は頭の病なんて恐ろしいものとは無関係、そう思いつづけることを許されていたから。
頭の病に対するひどい偏見。
けれど、自分はどこもおかしくないということを、みんなにも、そして自分にもしめしたいという思いが強かったがゆえ、家から一歩も出られないということにならなかったのも事実。
自分からしんどい、助けてなんて言うはずは絶対にない。
だから、これは病院につれていかなければ駄目だと母が思うほど、六年生のときにはもうすでに、かなり症状が進んでいたと思ってきた。
だが、大学入試はあれほど大変だったのに、ほとんど記憶に残っていないほど、あっさりと試験にパスし中高一貫のカトリックの女子校に入れたのだから、まだまだ序の口だったのかもしれない。
母の兄である道夫伯父さんの長男、次男、そして末の女の子も小学校から有名大学の付属校に通っていたし、あの時、母が私に私立中学の受験をすすめたのは、彼女の見栄からだと思っていた。
確かに、それも全くなかったわけではなく、同じく見栄っ張りの私はすぐに同意し、合格して彼女を喜ばせられたことが本当にうれしかった。
一年にみたない受験勉強で、特別成績がよかったわけでもない私が受かったのだ。確かに運はよかったのだが、偏差値はそれほどでもなく、しつけや校則の厳しい女子校という昔からのイメージでちょっとだけ名のしれた学校だった。
もっとも、私たちが在学していた頃というのは、愛校心の強い卒業生からはなげきの声があがるほど風紀の乱れていた時期だったらしく、下校途中、制服のまま喫茶店に入ったとか、授業をさぼって卓球をした、なんていう話を、後に友だちからもきいた。
そう、結局、皆が皆、校則やらキリスト教に基づく道徳やらにがんじがらめになっていたかといえばそんなことはなかった。
しかし、小学校のときから頭の固かった私はちがった。
十八で六年間通ったあの女子校を卒業し、大学というまぶしいぐらい自由に思えた世界に飛び出したのを機に、ひどかった強迫性障害の症状が少しずつよくなりだしたこともあって、一時期、あの女子校とともに、自分の見栄から中学受験をさせた母をうらんでいた。
けれど今は思う。確認行動などがふえてきた私が男の子たちにからかわれたりはしないか心配だったというのが一番の理由だったのだろうと。
私たちの年代だって、初恋は小学生のときという人は結構多いが、私は、小学校の六年間、クラスの男の子と一対一で話をしたという記憶がほとんどない。目は細く、おまけに左目は斜視。幼稚園のクリスマス会でマリア様や天使の役に選ばれるかわいい女の子たちとは程遠い外見。
同じような器量でも物怖じしない人だっているだろうが、私の場合は、すでに自分なんか男の子から相手にされるわけはないと思い込んでいたのだろう。
まともな恋愛もできないのは、中学、高校という大事な時期に共学にいけなかったからだと、さらに母をうらんだりもしたが、十二歳で男子のいない学校に入ったとき、喜ぶとまではいかなくてもほっとしたのは確かだ。
本当に相手にされていなかっただけかもしれないが、小学校でクラスの男の子からいじめられた記憶はほとんどない。けれど、小さいときに恐い思いをしたことは数回あった。
幼稚園のとき、不幸にして、ガキ大将が用を足しているトイレのドアを開けてしまい「何やってんだ、おまえ!」と、たてになってしまいそうなほどつりあがった目でにらまれたことはまだいい。
小学校一年のとき、他の学校の、おそらくは五、六年の男の子たちにからまれたときは心底恐かった。
たぶん彼等は、先生に告げ口されぬよう、たびたび自分たちの学区を出て他校の一、二年生を待ち伏せしていたのだろう。
あの日、下校途中、彼らに会ったのも初めてではなかった。前回、すれ違いざまに、リーダー格の男の子から向うずねを思いきり蹴られ、しばらくは地にその足をつけることもできなかったというのに、私には、横断歩道を渡り反対側に逃げることも考えつかなかった。
もしかしたらすんなり通れるかもしれないというわずかな期待にすがりながら恐る恐る近づいていく。しかし、彼らがようやくやってきた獲物を見逃すわけはなかった。先頭をきりすねを蹴ったあの男の子が道の真ん中に立ちふさがるとさすがに足が止まった。
あの痛みを再び経験するのはどうしてもさけたかった。
私は、精一杯の抵抗で他の子よりさらに背の高い彼をにらみつけた。
でも、それは右目だけで、矯正のため手術はしたもののコントロールしきれぬ左目は、完全に上にあがってしまっていたのだろう。
「おい、見ろよ、こいつ変な目してるぞ!」彼の言葉に、五、六人はいただろう、他の男の子たちもわざとらしい笑い声をあげはじめた。
絶体絶命のその時だった。
「あー、綾ちゃんだ。何やってるの、あんたたちー!」聞きなれた声が背後から聞こえ振り返ると、友ちゃんが靴袋を振り回しながら走ってくるのがみえた。そして、その後ろからは、兄を先頭に十人以上の三、四年生がどたばたと駆けてきたのだ。
「Z小のやつら、また一年生をいじめているのかよ」
「あんたたちの学校の先生に言いつけてやるからね」その勢いに兄たちより年上だろういじめっ子たちもあわてて逃げ出した。
その姿とともに、今となっては、涙が出るほどなつかしい思い出。それでも、小さい私は、友ちゃんたちに礼を言うこともできないほど固まってしまっていた。
あの時だけじゃない。幼稚園生のときも、公園で男の子たちにからかわれているところを助けてくれた友ちゃん、彼女も引っ越していなくなってしまったことだし、Z小の生徒たちと一緒になる公立の中学に進まず、女子校にいったのもそれはそれでよかったのかもしれない。
女子校にはいじめが全くなかったとはいわないが、少なくとも私の場合、戦う相手は自分だけだったから。
同じ制服を着て同じ学校に通った六年間、好きな人ができたわけでも、特別うれしいことがあったわけでもないから、中学のときと高校のときとで思い出を明確にわけることができない。だから、ひとまとめにして、中高時代は強迫症状が最もひどかったときといってしまおう。
指先ばかりか足の裏の神経まで過敏になって、登校途中、革靴の底でジャリなどという不快な感覚をとらえてしまうと、あろうことか、道路を壊してしまったのではないかという妄想にとりつかれた。
さすがに自分でもばかばかしくていったんは歩き出すが、やはり気になりまた戻り、大丈夫、誰かが怪我をするほど壊れていないと不安がる自分に言いきかせ、また歩き出す。それを繰り返し、ようやくたどりつく学校。
だが、トイレにでも行こうものなら、ドアのノブに棘がついてしまった気がする、手を洗った水が床に落ちてしまった気がすると、新たな悩みが次から次へとできていく。すべて気の済むまで点検するなどということは患った者にとって不可能。
とりあえず席に戻り、手帳に「とげ」だとか「水」だとか、帰るまでに再点検が必要な事柄をメモしていく。しかし、午後になるとその数が膨れあがり、何のことだか思い出せないものまででてくる始末。
忘れてしまうぐらいなら大したことはないだろうと割り切れるわけはなく、さらに不安が募っていくのが常だった。
責任を負わされることもない小学生のときに発症したのだ。
たとえば火の元の点検などは最初から命がけの作業だったわけで、そんなに大変なことではないと頭を切りかえるのはたやすくない。だから、今でも他の人より神経質だと思う。
しかし、眠っているとき以外は悩み事が頭から消えることのなかった中学、高校時代に比べたら、ずっとずーっと楽になったのだけは確かだ。
あの頃は、まだ、他人の人生も自分の人生も台無しにしてしまうような大きな失敗をやらかしてしまうことが恐いのだと、はっきり自覚できていたわけではない。
ただただ、恐怖や不安という圧倒的なエネルギーに突き動かされるように確認行動を繰り返していた。
それでも、体調をくずしたとき以外は休まず学校に通いつづけられたのは、自分はどこもおかしくないということを証明したいという切実な思いとともに、さらに六年間を過酷なものにしたバレーボールのおかげだったのかもしれない。
のろまでぱっとしない自分から脱却する絶好のチャンス。今までの私を知る人のいない中学に進むと惰性で続けていたバレエをやめバレーボール部に入った。
固い頭はすぐに体育会系の努力、根性至上主義にはまり、バレエのときとは一変、人一倍練習した。もちろん、努力すればテレビの主人公みたいに、どんな強打もレシーブし、アタックをビシバシきめるチームのエースになれると思っていたのだ。ところがだ、悲しいかな私の場合は、練習しても練習しても全くうまくならなかった。
腹筋は百回以上できるようになったし、腕だって足だって鍛えあげずいぶんたくましくなった。それでも、いざボールを扱うとなると気持ちがあせるばかりでタイミングが全然あわない。
今、振り返ると、頭やら神経系統やらに何らかの障害があったのではないかと思えてしまうほどだ。
頭と身体が覚えていくのは練習の厳しさばかり。少しもうまくならなければ入部当時の興奮も冷めていく。楽しくなんてなかったのだからやめればよかったのだ。
しかし、カチンコチンの頭は途中でやめれば負け犬だと完璧に思い込んでいた。いつの間にか私の目標は、六年間バレーボールをやりつづけるというただそれだけになっていた。
練習中だって病的な不安感が消えるわけではなかった。
けれど、行きつ戻りつしていた通学途中の坂道。足腰をきたえるため走り通そうと決めたときには、手に重い鞄をぶらさげて一気に駆け上ってもいたし、何より、学校は休めてもバレーボールの練習を休むなんて私には考えることもできなかった。
そんなこんなで、強迫症状が最もひどかったときも学校に通いつづけられたわけだが、中学、高校の六年間、アイドルだって好きになることはなかったし、おしゃれどころか鏡に自分の姿を映すことさえほとんどなかった。友達に悩み事を打ち明けることもなければ、ひとり自分の将来を思い描くこともない。
ただただ、病を抱えバレーボールを続けることだけに懸命で、女の子が一人前の女性になるために必要な過程を自分はほとんどすっ飛ばしてしまったような、そんな気もする。