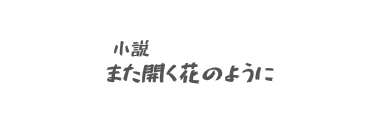マリア様に会いたい

「あなたのオーラは……」そんな言葉がテレビからきこえてくる今とは時代だって違う。友ちゃんが道ですれ違った人を振り返り、「うわー、あの人なんてきれいな色に囲まれているのかしら」と、言ったときも、ワンピースの色のことかなぐらいにしか思わなかった。
「俊ちゃん、俊ちゃんの後ろでね、とっても優しそうなおじいさんがほほえんでいるよ。あは、『はい、こんにちは』って私にあいさつしてくれた。そうだ、仏壇に写真があったじゃない。俊ちゃん、綾ちゃんのおじいさんだよ」なんて言い出したときも、
「えー、どこ? 誰もいないじゃない。お兄ちゃんの後ろは空気だけじゃない」と、言い返した。
しかし、友ちゃんが語る人間ではない存在たちはいつだって怖くなくて、魔法使いやら妖精やらが出てくる本と同じように私を夢中にさせてくれた。
あれは兄が小学校の卒業証書をもらってまだ間もない春休みのこと。
さすがに学年が進むにつれて三人そろって遊びにいく回数はへっていたのだが、あの日は、春の陽気にさそわれたかのように、友ちゃんが我が家に声をかけてくれた。
「俊ちゃん、綾ちゃん、お母さんがサンドイッチ作ってくれるから、それ持ってお昼からS公園にいってみようよ」
線路の反対側にあるS公園は友ちゃんのお気に入り。桜はまだ早咲きの一本が開いているだけだったが、入り口の木蓮は大きな白い花をつけていた。
「ねぇ、昨日、夜中に目を覚ましたらね、ベッドのよこにマリア様みたいな格好をした外国の女の人が立っていたんだよ」友ちゃんがそう言い出したのは、芝生の上にビニールシートを広げてサンドイッチを食べていたとき。
「夢じゃなくて?」
「うん、夢じゃない。だってあの人が私の部屋にきたのはじめてじゃないんだもの。一年生になるまではね一年間に何度も会いにきてくれてたの。でも、小さかったから夢の中の人だと思ってたんだけど、昨日、夢じゃないってはっきりわかった」
「おばさんの友だち?」
「違うよ俊ちゃん。玄関にも窓にも鍵がかかっているのに私の部屋にぱっとあらわれるんだよ。あの人は私たちと同じ人間じゃないんだよ」
「じゃあ、お化け?」
「お化けでもないよ。だってちっとも恐くなかったもの。天使やマリア様みたいに私たちを守ってくれてる人だと思うんだ」
「その人なにかしゃべったの?」
「外国の人だからね。日本語しゃべれないんじゃないかなー。声はきいてない。でもね、私にはわかったの。
俊ちゃんも中学生になるしさ、ずっと今のままではいられないじゃない。これからは、きっといろいろ変わってく。だけど、恐がらなくていい、ひとりじゃないからって、あの人、私に言いにきてくれたんだ」
その後の変化を知る今では思い出すたびにどきりとさせられる友ちゃんの言葉。けれど三年生を終えたばかりの私には、特別な人が友ちゃんの前に現れたということしかわからなかった。
三年間、クリスマスにはみんなでイエス誕生の劇をするようなカトリックの幼稚園に通ったことも影響していたのだろう。小学校で、同じクラスの真美ちゃんに首からさげているマリア様のオメダイを見せてもらってからキリスト教に関心を持ちはじめ、大きな教会の日曜学校にもついていったばかりだった私は、胸をどきどきさせながら言った。
「ねぇ、その人、本当のマリア様なんじゃない?」
「そうかなー、よくわかんないけどね」友ちゃんの返事はそっけなかった。けれど、すでに思い込んでしまっていた私は、
「私もマリア様に会いたいな」と、ライバルであるはずの彼女に素直に言った。
すると、
「僕も会いたい」と、もうすぐ中学生になる兄もとなりでまじめな声をあげた。
「じゃあさ、俊ちゃんが中学生になるお祝いだっていってふたりでうちに泊まりにくれば?」
ゴーという音をたて、青い空のどこかを飛行機が横切っていく。私は、ごくりとつばを飲んでから、兄と一緒にうなずいた。
旅行先で三人枕を並べて寝たことは何度もある。けれど、家が隣同士だと、どちらかの家で晩御飯をたべても、「こんな時間になってしまったからうちに泊っていきなさいよ」なんてことにはならない。
私が生まれるとき、兄が友ちゃんの家にあずけられたという話しはきいていたが、私自身があの時以外で友ちゃんの家に泊ったという記憶はない。
それに、いくら兄弟のように育ち、あの頃の子供は今よりずっと幼かったといえ、中学生になる兄をひとつ年下の友ちゃんの部屋に泊らせるということについて親たちはどう思ったのだろうと考えてしまったりもする。
しかし、何はともあれ、翌日にはおばさんがうちまで来て母と話をしてくれて、卒業祝いという名目のお泊まり会は春休みのうちに決行されることとなった。
誰が寝るかで喧嘩になってはいけないと思ったのだろうか。あの日、おばさんにおやすみを言って、階段を上り友ちゃんの部屋にいくと、ベッドの前にはすでに三組の蒲団がひかれていた。
「俊ちゃんは男の子だから真ん中ね」友ちゃんの意見に私も不満はなく、兄をはさむ形で三人が布団に入ったのはそんなに遅い時間ではなかった。
待ちに待った夜だ。もちろん私はマリア様が現れるまで寝るつもりなどなかった。
「俊ちゃん、俊ちゃんは大きくなったら何になりたい?」
「僕、ミケランジェロみたいに大きな像をつくる人になりたい」
「へー、そうなんだ、絵を描く人じゃないんだ。ねぇ、綾ちゃんもバレリーナの他になりたいものがある?」
「うーん、学校の先生もいいな」
「結婚してお母さんには?」
「もちろん、なるよ」
「友ちゃんは?」と、兄。
「私? 私はね、アメリカもフランスも、インドも行ってみたいからスチュワーデスにもなりたいし、洋服つくる人にもなりたいし、パパみたいな絵描きさんにもなりたいし……うーん、ケーキ屋さんも花屋さんもいいな」
「そんなにいっぱいあるの……」
「そう、いっぱいね。ねぇ、じゃあ、俊ちゃんは中学生になったら美術部に入って、高校卒業したらパパと同じ上野の学校にいくの?」
「うん、いきたい」
「へー、俊ちゃん、いくんだ。そうか、動物園も近いし楽しいだろうな。なんか私もいきたくなっちゃったな。絵の学校卒業したって、スチュワーデスにもなれるよね?」
「大丈夫だよ。一緒にいこうよ」
相変わらずにぎやかな友ちゃんの声。いつだって彼女が中心。彼女と離れて寝ている私にはなかなか会話がまわってこない。面白くない。泊まりにおいでと言ってくれたことで忘れていた彼女に対するマイナスの感情がふつふつと湧きあがってくる。
友ちゃんもお兄ちゃんも早く寝ちゃえばいいのに。(マリア様、あなたに本当に会いたいと思っているのは私なんです。どうぞ、どうぞ今夜は友ちゃんじゃなくて、私だけに会いにきてください)私は目の上まで布団を引き上げ、マリア様相手に話しはじめる。
しかし、それがいけなかったのかもしれない。五分も経たずに目蓋がおりてきてしまったのだ。はっとして目を開いてもまたすぐおりてきてしまう。
紅白歌合戦をみる大晦日だってプレゼントが届くクリスマスだってちっとも眠くならなかったというのに、どうしてあの日だけと今も不思議に思うほど、それは突然で小さな身体にはとても逆らえぬ眠気だった。
あきらめた私は隣りに寝ている兄の腕をつかみ、
「ねぇ、交替で寝ようよ」と、小さな声で言った。
「いいよ」
「じゃあ、私が先に寝る。しばらくしたら起こしてね。絶対に起こしてね」
一方的な言い方に兄が文句を言ったのかしぶしぶ了解してくれたのかは覚えていない。たぶん、それを聞く前に私は眠りに落ちてしまったのだろう。そして、そこから戻ってきたのは、黄色のカーテンを通して日の光が差し込む朝。
兄にどうして起こしてくれなかったのと言えぬどころか、「綾ちゃん、昨日、あっという間に寝ちゃったね。あれからマリア様が会いにきてくれたんだよ」と、言われるのが恐くて、彼らの顔さえまともに見ることができなかった。
そのせいか、あるいは私とそう変わらずにふたりとも寝てしまったせいなのか、幸いにして、おしゃべりな友ちゃんからさえ、あの夜の話を聞くことはなかった。