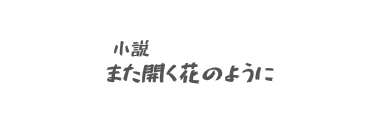奇抜なファッション

検査入院は十日間。内科的な病はみつからなかったが、その間、父は、兄と一緒に脳神経内科を受診して自分の病のことを直接医者からきいた。
それでも、病室が重苦しい空気に包まれることがなかったのも、特に何をするわけでもなかったが、ほぼ毎日のように病院に顔を出してくれた友ちゃんの存在がやはり大きかったのだろう。
しかし、私が彼女のことをすっかり信頼できたかといえば、そうもできない事情があった。
あれは、バイトが休みで午後二時頃病院にいったときのこと。
ちょうどお昼寝タイム。三〇五号室に入るとあちらこちらから寝息やいびきが聞こえてきて、お舅さんに付き添っていた年配の女性と目で笑いあったほどのどかな時間が流れていた。
私は足音をしのばせ、奥へと進んだが、もっとも大きなクーカーといういびきがカーテンで囲まれた父のベッドから聞こえてくることに気づいたときは、思わず、
「あらら」と、声を出してしまった。
笑いながらそっとカーテンを開け中をのぞくと、なんと眠っているはずの父と視線がぶつかった。それじゃあ、一体? 視線をずらすと、パイプ椅子に大きなお尻だけ残し、万歳までして父の布団の上に突っ伏した友ちゃんが、病室中に響いていたあのいびきをかいて熟睡しているではないか。
「と、ともちゃん」あわてて起こそうとした私を、
「起こすな」と、父の小さいが強い声が制した。
あきれはて焼き餅をやく気にもならなかったが、自分の方を向いた寝顔を枕の上から覗きこむ父の目はとても優しく、私は彼の言葉に従い、友ちゃんの隣りにパイプ椅子を広げて座った。
ふと目に入ったのは万歳をした友ちゃんの手。洗っても落ちなかったのだろう。指先は絵の具で染まっている。昨日も遅くまで描いていたのだろうか。鎌倉から毎日この病院に通うだけでも疲れるだろうに。
父ほどではなかったにしろ、私もまた友ちゃんをいとおしく思った。
しかし、病室に看護師が入ってきてカーテンの外があわただしくなると、彼女はようやく目を覚まし、
「ああ、寝ちゃった」と、言ったあとに、
「お昼ご飯の後で間違えて眠剤飲んじゃった」と、付け加えた。
飲むなよ、私は、目をこする彼女を横目でにらんだ。
そんなこんなで、もしかしたら面倒をみる人が二人に増えるかもしれないという不安がぬぐえず、バイトの休みを変えて父の通院に付き添えるようにしたり、電動式の介護ベッドを借りたりと、退院後、ひとりで彼の世話をする準備を進めた。入院する少し前まで、バイトから友達と飲み屋に直行して、父を夜遅くまでひとりにしておくこともあったのだから、一ヶ月ぐらい、友ちゃんに頼らずとも乗り切れるだろう、そんな気もしていた。
しかし、退院の日からバイトも数日休み父に付き添った私は、あっけなくこれは無理だと白旗をあげた。
たかが十日間の入院でも、私に心配かけまいと精一杯頑張ってきた父には長かったのだろう。
私が近所に買い物にでかけた数十分の間にトイレにいき、あやまって手前のドアから三十センチほど低くなった風呂場の床に転げ落ち、ばったり倒れて動けなくなっていたときには悲鳴をあげてしまったし、数日だけはと父の隣り、ソファーの上で寝たところ、夜中三度もトイレに付き添うこととなりすっかりリズムが狂ってしまった。
「アロマの講座がはじまる前の週から火、金は泊りにいくから」と、言ってくれていた友ちゃんは、私の曖昧な返事などまるで気にしていなかったようで、月曜日の夜には、
「お父さんを起こしちゃうといけないから、合鍵持っていって、勝手に入らせてもらうね」と、電話をくれた。
翌日は、退院後はじめてバイトに行く日。アロマの講座がなくとも父のことが心配だったから、昼頃には家に来てくれるという彼女の言葉にまたまた救われ、こうして週二回、友ちゃんが我が家に泊るというにぎやかな日々がはじまったのだった。
父の退院の日、彼が乗った車椅子を押す友ちゃんのサンダルのかかとが高く不安定だったため、私が注意したからだろう。アロマの講座を受け、夜九時頃家に帰ると、玄関には灯りがついていて、そこには、友ちゃんの赤いズックが並んでいた。そして、眠り込んでいないかぎりは、「おかえり」と、彼女自身も玄関まで出てきて笑顔で迎えてくれた。
病室でいびきをかいて寝ていたことを思えば、呼ばれて目を覚ますか甚だ疑問だったが、父のベッドを設置した居間の隣り、奥の座敷に、襖をはさんで互いの頭が二メートルと離れないよう布団を敷き
「これで大丈夫」と、言っていた友ちゃんに甘え、火、金の夜だけは二階の自分のベッドでぐっすり眠らせてももらった。人一倍睡眠の必要な私にとって、それは大きなことだった。
そして、もうひとつ大きかったことといえば、あの一ヶ月の間に、お洒落の楽しさを教えてもらえたこと。
「ねぇ、綾ちゃん、私、太っちゃって着れない服がたくさんあるんだけど、着てくれる」そう言った次のときから、彼女は大きな鞄プラス紙袋にいっぱいの洋服を詰めて我が家にやってくるようになった。
「服だって、思い込みが強すぎると、自分にぴったりなものを見逃しちゃうからもったいないよ」そう言って、彼女は次々と私の顔に洋服を合わせていくのだが、確かに、自分では絶対買わないような意外な服が私を引き立ててくれるのには驚いた。
化粧も教えてもらったし、友ちゃんは、太っても最高のファッションアドバイザーだった。
けれど、不思議なもので、彼女自身のファッションは、私などには全く理解できぬほどぶっ飛んでしまうことがたびたびあった。
退院したばかりのときは、このまま二十四時間、介護が必要になっていくように思えた父だが、日が経つにつれ落ち着き、ケアマネジャーや業者さんのアドバイスでそろえた介護用品を上手に使いこなせるようになり、転ぶこともなくなった。
残業がなくバイトから早く帰ると、彼は大概パソコンに向かっていて、また仕事をはじめたのかと思うほど真剣な顔をしていた。
通所施設の見学にいきたいと言い出したのも、たぶん、私や友ちゃんに負担をかけたくないという思いからで本意ではなかったのだろう。
けれど、あの時の私には、それがわからず、独りの時間が長くてぼけでもしたら大変だと思ってもいたから、さっそく、家から一番近い通所施設を見学する段取りをつけた。先方の都合と私がバイトを休める日ということから金曜日の午後に決まったのだが、たまたまその日は、友ちゃんが夜、友達の出版記念パーティーに行くとかで、昼過ぎには来てくれるものの、夕方からは、兄とバトンタッチして父をみてくれるといっていた日だった。
忙しくてなかなか我が家に顔を出せぬ兄はその日ならとはりきっていたから、アロマの講座のために来てもらうとしても、私がバイトを休み父と出かけるのであれば、友ちゃんにわざわざ来てもらう必要もない。
そこで事前に電話をいれたのだが、
「もし、お父さんが通うようになったら私がお迎えにいくこともあるだろうから一緒に行くよ」と、彼女は言った。通うことになったら車で送迎してもらうつもりでいたのだが、行く気満々なのにことわる理由はない。昼食をとってくるという彼女を待って三人で見学にいくことになった。
節電のため冷房の設定温度を二十八度以下には滅多にしない私だが、耐えられず下げたほど暑い日だった。
これじゃあ、車椅子に乗っていたとしても父が暑さでまいってしまう。タクシーの後ろに車椅子を載せてもらって施設まで行ったほうがいいと私は考えていた。
けれど、父は暑さなど全く気にならない様子。三人で出かけるのがうれしいらしく、
「施設見学はまた今度にして銀座にでも行くか」と、言いながら、自分で服を選び早々に仕度をすませていた。
十二時半に来ると言っていた友ちゃんだったが、十二時少し過ぎ、私たちがまだ食事をしているときに玄関のベルが鳴った。
私は、彼女がいつもしてくれているように、玄関に出迎えにいった。
「いらっしゃい」そう言いながらドアを押す。しかし、ポシェットをのぞきこみ一生懸命、鍵をさがしている彼女の姿を見た瞬間、ぎょっとしてしまった。
結ばずにおろした髪は金色。タンクトップから突き出た太い腕の片方には、実際にはシールだったのだが、刺青のような蝶が。そして、一番驚いたのはタンクトップとアジアンチックな長いスカートの間に満月のようなお腹がのぞいていたこと。
「鍵がみつからなくて」ポシェットから顔を上げた友ちゃんは、私を見てほっとしたように笑ったが、たとえ我が家で着替えてから施設の見学に行くつもりでいるとしても、彼女がこの格好で電車に乗ってきたということがショックで、口がきけない。父に見せるのも気の毒に思えたが、私は無言で居間に戻った。
案の定、私の態度がおかしいと気づかない友ちゃんは、後ろから、
「こんにちはー」と、陽気な声をあげて入ってきた。
私は横目で父の反応を見ていたが、なんと彼は、実に楽しそうに笑ってから、
「友ちゃん、今日は山本リンダみたいだね」と、言ったのだ。
(な、なにが山本リンダだ!)私には、なぜ彼が笑っていられるのか全く理解できなくて、
「今日は、施設見学でも銀座でもなくて、カラオケにいくか」というのを無視し、自分の食器だけまとめて台所に引っ込んだ。
蛇口をひねり流れ落ちる水を見つめながら気を落ち着けようとするがうまくいかない。
それなのに、
「綾ちゃん、ゼリー買ってきたんだけど一緒に食べよう」と、友ちゃんは後ろからのん気な声で私を呼ぶ。私は、くるりと振り返り彼女に向かって手招きをする。そして、
「なーに?」と、彼女が台所に入ってくるとそっとドアを閉め、小声で訊いた。
「着替え持ってきたの?」
「持ってこないよ」
私の脳裏に、幼い頃、互いに手が出るほどの喧嘩となったいくつかの場面がうかんだが、それでも、言った。
「じゃあ、家で留守番していて」と。
しばしの沈黙。彼女にじっと見つめられ、私の心臓はどきどきと音をたてていた。しかし、小さく頷いてから彼女は言った。「わかった、Tシャツ貸してくれる」と。
髪は金髪でも、刺青にみえる蝶と丸いお腹がTシャツでかくれるとそれほどひどくはなくなったので、結局、三人で施設見学にいったのだが、夜には友達の出版記念パーティーに参加したのだろう義姉である彼女のあの格好は、しばらくの間、思い出すたびに私の気持ちを暗くした。