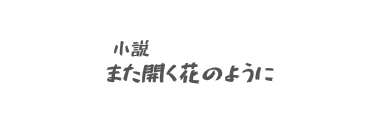不思議な人

父さんだって、彼女が来ると知ったら大喜びして、私が検査結果をききにいったことなど忘れてしまうかもしれない。私は、兄の携帯に電話するのも後にして、父の病室にもどった。しかし、昼食をとったのだろう彼は、スースーと寝息をたてていたため、これ幸いと、看護師さんに用事があるから三時にはもどると言いのこし、病院から抜けだした。
外の空気を思いきり吸うと急にお腹が空いてくる。考えてみれば、朝のドタバタで朝食もとっていないではないか。
コンビニでお弁当を買ってかえりテレビをみながらゆっくり食べて、入院に必要な品々をそろえたら、あっという間に二時半ちかくになっていた。
友ちゃんより先に病院に戻ってなきゃなと、近所の店で足りなかった物を買いたしながら病院へと向かう。
六月だというのにやけに暑い日で、空は真っ青。その空の下、向こうから、遠くからでもわかるほど太った女性が歩いてくる。自分だって痩せているとはいえないのだが、あの体形では、この暑さ、かなりきつかろうと、私は勝手に想像する。
ところがだ、顔から汗が噴きだし、肩で息をしながら歩いてくるものと思いきや、近づくにつれそうではないことに気づいた。
小花模様の長いスカートをはいた彼女は、まるで時々吹いてくる心地よい風を全身で感じ楽しんでいるかのように、軽く両手を広げ遠くの空をながめながら歩いてくる。その顔はなぜとききたくなるほど無邪気で幸せそうで、何らかの障害がある人か、あるいは天と交信する人か、そのどちらかかと思った。
不思議な人だ。心の中でつぶやきながら十字路を左に曲がろうとしたその時だった。
空を見ていた彼女の視線が下がってきて私とぶつかり、そして、彼女はにっこりと笑った。
「と、ともちゃん?!」失礼だったかもしれないが、私は思わずきいていた。
「そうよ、綾ちゃん、ひさしぶり」四十二とは思えないほど、笑顔は愛嬌があって可愛いといえば可愛かったし、南の国のどこかには彼女のような女性を絶世の美女とするところもあるような気がした。けれど、日本人である私は、スタイルのよかった彼女があまりにも太ったことに、ともかくびっくり仰天してしまった。
兄の婚約者として私の前にあらわれたとき美しい大人の女性へと変身していたことにも驚いたが、あの時以上だったように思う。
正直、父が友ちゃんとわかるだろうかと心配になったほどだった。
でも、それは杞憂だったようだ。
六人部屋である父の病室にいき窓際のベッドをのぞきこむと、彼の目は私たちの方へと動き、そして、顔をくずした彼の口から
「ああ、友ちゃん」と、本当にうれしそうな声がもれた。
「なんだ綾、検査入院なのにわざわざ電話かけたのか? すまなかったね」
「私の方こそ、長い間、心配かけちゃってごめんなさい。もう大丈夫ですから、私にできることがあったら何でも言ってくださいね」
そう言った友ちゃんだったが、変わったことといえばただ太ったことだけ、というわけにはいかなかった。
たとえば、彼女の携帯がメロディーを奏ではじめたときのこと。私が、
「病院では電源を切らなきゃいけないんだよ」と、注意すると、なんと友ちゃんは一度も電源を切ったことがないらしく、
「電源ってどうやって切るの?」と、きいてきたのだ。ところが、私の携帯は、お年寄りでも使える一番シンプルなもので電源と書いてある大きなボタンを押せばいいだけだったが、彼女のは違っていて手におえない。
「わからないや」と、言うと、
「じゃあ、ナースステーションいってあずかってもらってくる」と、すたすた病室を出ていってしまった。ちょっとしてから、
「看護婦さん、電源切ってくれた」と、うれしそうにもどってきたが、私はとても恥ずかしかった。
そんな以前の彼女なら考えられぬ言動が何度かあったわけだが、それでも、父の表情がくもることはなく、ふたりはとても楽しそうに会話を交わしていた。
もし、三年という月日が経っていなければ違ったかもしれないが、父の夕食がすんでから帰るつもりでいたもののMRIの結果をきかれるのが恐い私は、一方的にしゃべりつづけるわけでもない友ちゃんが少しでも長くいてくれたらいいなと思っていた。
ところが、夕方の四時になると、父の方から
「綾も友ちゃんとひさしぶりに会ったんだろう。父さん、病院じゃ困ることないからもういいよ。二人でお茶でも飲んだらどうだ」と、言ってきた。たぶん、あまり遠出をすることもないと思える友ちゃんを気づかったのだろうが、彼女は全く苦でないらしく、
「そうそう、忘れてた。家を出るちょっと前に俊ちゃんから電話があったんだった。明日夕方ここに顔を出すって言っていましたから、私もまた来ますね」と、にこにこしながら父に言った。
それから病院を出た私たち二人は、急行の止まる駅までぷらぷらと歩いていき、イタリア料理店に入った。
太った友ちゃんは、動きもしゃべりもとてもマイペースで皆の注目をあつめそうだったから、私はちょっと恥ずかしかったのだが、ひとり悶々とこれからのことを考えるよりは彼女と一緒にいたいと思った。
「薬、飲んでいるし、私はあまり飲めないんだけど、綾ちゃんは飲んでね」そう言われたら遠慮すればいいのに、私はグラスワインの後でさらにビールを注文し、グイッと飲んだ。
目の前でおいしそうにスパゲティーを食べている友ちゃんは、時々、紙ナプキンで拭くものの口元がトマトソースで赤くなっている。
美しくはつらつとしていた友ちゃん。画家、染野友の外見に惹かれていたファンも多かったことだろう。もうかなりの枚数が描けているのに次の作品展の予定は立っていないと父に言っていたが、もしかしたら、以前、彼女を高く評価し応援していた人たちも、皆、離れていってしまったのかもしれない。そんな想像から、より親しみを覚えたのとアルコールのせいだろう。私は、事故にあうまえの彼女にだったら言わなかっただろうことを打ちあけていた。
「実は、私さ、新しい仕事をさがしていたんだ」
「何かやりたいことがあるの?」
「違うよ。私ね、友ちゃんたちがうちの隣りから引っ越しちゃってすぐ、まだ小学生のときに、強迫神経症っていう病気になっちゃったんだけど知ってる? 手にばい菌がついているような気がして何度も洗ったり、火の元の点検を繰り返したりする病気なんだけど」
「うん、わかる」
「大学入ってから、いかにも病気っていう症状は消えたんだけど何やるにしても不安が強くてさ、楽になりたいってそればかり考えているうちに四十になっちゃってさ。恥ずかしいけど郵便局のバイト代なんて微々たるもので、経済的に全然自立できてないし、貯金もないし、これじゃあいけないってようやく気づいてさ」
友ちゃんは私をみつめているだけで何も言わない。しゃべってますます自分のことが情けなくなった私は、また、ビールをグイッと飲んだ。
「ねぇ、綾ちゃん」彼女の声がしたのは、テーブルにおいたグラスの中をのぞきこんでいたとき。
「なに?」
「前にくらべればずーっとすっきりしたんだけど、それでも、まだ私には見えるんだよ」
「え、なにが?」
「頭の周りにね、ああじゃなきゃいけない、こうじゃなきゃいけない。ああだからこうだ、こうだからああだっていう思い込みがもやもやとさ」
「本当に見えるの?」
「うん」友ちゃんは大きくうなずいた。
「このもやもやが、もっと消えたら身体も心も楽になるのにね。綾ちゃんは綾ちゃん、人と比べることなんて何にもないんだよ」それから、彼女は手を伸ばしてきて私の頭の周りにあるらしい何かを一生懸命払おうとした。
けれど、うまくいかなかったのだろう。彼女は話題を変えた。
「ねぇ、アロマを学びたいって、言っていたよね?」
「ああ、そう言っていたときもあったよね」
それはすでに四年も前のこと。美術学校を卒業し、母も亡くなり、いよいよ働かなければいけなくなったものの、自分ができる仕事も、やりたいと思う仕事もみつけられず暗澹たる気分になったとき、画家に続いてアロマセラピストになりたいという無謀な夢に逃げ込んだ。おそらく、その時、友ちゃんにも話をしたのだろう。
ボディーワークを受けて、自分の体にも問題があったと気づいてから、日に日に、それが、感情的な問題や処理能力ばかりか強迫性障害にも関係していたと確信するようになっていった私の中で、体について学びたいという思いが芽生えていたのは確か。
そして、今度は自分がボディーワークを行う人になりたいという憧れもあった。
でも、じゃあ、本当にアロマセラピストになり今より収入を増やせるかといえば全く自信が持てなかったのであきらめた。
それでも、アロママッサージへの関心が消えたわけではなかった。だから、友ちゃんに、
「ずっと前に絵をみにきてくれて知り合ったんだけどね、今じゃ、マッサージの予約もなかなかとれないほどのセラピストさんが学校開いているんだけど、どんなものか初級講座だけでも受けてみない?」と、言われたときはちょっと心が動いた。
でも、父の病気を知り、新しい仕事探しも中断しようと決めた自分に、そんな贅沢をさせるわけにはいかない。
「私、絵だってあんなに学校通ったのにもう描いてないし、また無駄になっちゃう気がするから……」
すると友ちゃんは、子供の頃ならともかく、蝶のように美しかったときなら絶対に言わなかっただろうほどずばりと言いきった。
「もう、綾ちゃんて、ほんと頭かたいね!」あまりの勢いに、言われた私も笑ってしまったほどだ。
「初級はさ、半分、遊びなんだから少しでも関心があるなら難しく考えることなんてないんだよ。待って、パンフレット持ってきたんだった」彼女は大きな鞄の中をがさごそと長い間かきまわしてから、「あった」と、満足そうに言った。
「えーと、火、金の夕方六時からっていうのがあるよ。七月十三日から全部で八回。そうだ、綾ちゃんが帰ってくるまで、私が家でお父さんと一緒にいるから、バイト終わってからどこかで食事していけばいいじゃない」
「それじゃあ、大変だよ」
「大丈夫、おじさんには本当にお世話になったんだしさ。そうだ、その日は泊めてもらって、夜中、お父さんがトイレいきたくなったら私が手伝うよ。料理はへたくそになっちゃったから作れないけど買えばいいもんね。次の日も、一緒にお昼食べてから帰れば、火、水、金、土は、綾ちゃん、安心してバイトいけるでしょう?」
「うん……ところで、講座っていくら?」
「心配しないでよ。やりたいことがあるなら応援させてよ。ここに名前や住所書いて。私がFAXして代金払い込んでおくからさ」
勢いに押され申し込み用紙に記入すると、彼女はそれを手にしてから言った。
「私ね、これからは俊ちゃん以上に綾ちゃんにお世話になるような気がするんだ」
「そ、そうなの?」笑いながら返したものの、兄はせっせと人形を作り、歩けなくなくなった父と、少し調子のはずれた友ちゃんの面倒を私ひとりがみるという未来が頭にうかび、それだけは勘弁と心の中でつぶやいた。
それでも、お腹いっぱい食べて飲んでしたあの夜、何も思い悩むことなくぐっすり眠れたのは間違いなく彼女のおかげだったのだろう。