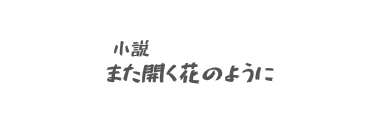初めてきく頭の病

父の通院に付き添うため休みをとっていたあの日も、朝早く起き、パソコンを開き、行動を起こさなければ何も変わらない。今日こそ、この職場に電話をしてみようと決意をかため、それから、一階におりた。
脳神経内科の予約は十一時。出かけるまでにはまだまだ時間があったが、まずはゆっくり朝食をとるつもりだった。
しかし、居間のドアを開けると奥の座敷から、また、
「綾子、綾子」という父の弱々しい声が聞こえてくるではないか。
「どうしたのお父さん?」
「胸が苦しいんだ」
「いや、その必要はない」
「じゃあ、もうすぐ病院が開くから先に内科を受診する?」
「ああ」
大丈夫だ、脳神経内科の先生に相談してみる、とは言わなかったのだからかなり苦しかったのだろう。
幸い、病院は歩いたって十分とかからない距離。タクシーならあっという間。トレーナーの上下のまま病院に着いた父は、車椅子に乗せられ、血圧を測ったり心電図をとったり。でも、特に異常はみつからなかった。
あの夏はともかく暑くて、六月だというのに寝苦しい夜が続いていたから、それで体調をくずしたのではないかと今では後悔している。しかし、暑さ寒さの対策ぐらい当然ひとりでできるものと思っていた私は、異常なしとわかったとき、ほっとすると同時に、しっかりしてよお父さんと、心の中でつぶやいていた。
だから、医者が
「検査のためしばらく入院しますか?」と、言い出したことは予想外だったし、父が、
「はい、お願いします」と同意したのにも驚かされた。
けれど、私が気づいていなかっただけで、あの時、彼には、ひとりで頑張る限界がきていたのだろう。一階でベッドが用意されるのを待つ間中、車椅子の上でじっと目をつぶっていて、入院する必要ないんじゃない? なんて、とても言えない雰囲気だったし、ようやく病室に連れていってもらえると待っていたかのようにベッドの上に身を横たえた。
「綾、すまないが、脳神経内科の先生から結果きいてきてくれよな。もし、言いにくいことがあったら言わなくていいから。来週にでも自分でききにいく」そう言ってから、ニヤリと笑うだけの余裕はあったが、毛布の上からだと、彼の身体がますます小さくなってしまったようにも思えて、これからの検査によって悪性の腫瘍でもみつかってしまうかもしれないと不安になった。
脳神経内科には、看護師を通して、私が一人で結果を聞きに行く了承をえていた。
一週間、父を見てきたが、脳梗塞を起こしたとは思えないし、問題があるとしても、やはり頭ではないだろう。
私はMRIをながめる医者が
「特に問題ありませんね」と、言うのを待った。
ところが、彼はなかなかそう言ってくれなくて、ようやく口を開くと
「この部分、脳幹なんですけどね、ここにかなりの萎縮がみられますね」と、難しい話をしはじめた。もちろん、素人の私がMRI画像をのぞきこんでも正常かそうでないかなんてちっともわからなかったし、一番大きな大脳ならともかく、そんなところが萎縮しているからってだからどうなの? と、いう感じでしかなかった。
それは、医者が、生まれてから一度も耳にしたことのない病名をあげ、それにほぼ間違いないと言いきったときも同じで、どんな病気か知らないのだから反応のしようがなかったし、名が知られていないのだから大した病じゃないような気がした。
だが、
「バランスが悪くなり、転倒しやすくなるのが特徴のひとつなんです」と言われたときは、さすがにどきりとした。
「あります。朝、私が起きてきたら、父が床に転がっていて起きあがれなくなっていたことがありました」
「ええ、手で身体を支える余裕もないぐらい、パタンと、時には後ろに倒れることもありますから、頭を打ったり骨折したりする危険性も高いんです。
人によってかなり差がありますが、進行性の病で、いずれは歩けなくなるケースがほとんどですし、飲み込みに問題が生じ肺炎を起こしたりして数年で亡くなる方も多いです」
数年で亡くなる?
患者やその家族に、一般的に知られていない病の恐ろしさを伝えるというのは、医者としても難しいことなのだろう。彼がさらりといった言葉は、私をゆっくり打ちのめしていった。
「胸が苦しいと言ってさっき入院したのですが、関係あるでしょうか?」
「いや、それはないと思いますよ」
「私も昼間は仕事にいっていますし、今はすべて自分のことは自分でやってくれているのですが……」
「うーん、これだけ、萎縮が進んでいますから、一人だと立ち上がるのもきびしいように思いますが……」
「いずれ、一人にしておけなくなるときがくるでしょうか?」
「その可能性は非常に高いですね」
ボーッとした頭で診察室を出たが、エレベーターの前に立ち、父の病室にもどらなければいけないと気づいたとき、悲しみがどっと込み上げてきた。
のろまだろうが、不器用だろうが、厄介な病にかかりおかしな行動を繰り返そうが、嫁にいかなかろうが、定職につかなかろうが、それでも無条件で愛してくれる人なんてお父さんしかいない。そのお父さんがいなくなってしまう……。
彼に二十四時間付き添わなければいけなくなる日がくることはそれほどショックではなかった。それよりも、彼がひとりで病と戦ってきたことが悲しかった。
エレベーターが開く直前、乗っている人に涙を見られるのがいやで、私は、横の階段にまわり、一階へとおりた。
医者に言われたことをお父さんに言うことなんてできないよ。どうしよう、お兄ちゃん⁉︎
携帯電話を家においてきたため、公衆電話の受話器を持つと、三年間自分からかけることのなかった兄の家の番号を押した。
どうかお兄ちゃんがでますように、心の中で祈っていたのだが、十回ちかい呼び出し音の後で聞こえてきたのは、彼ではなく友ちゃんの声だった。
「はい、山瀬です」聞こえぬよう溜め息をついてから、元気?の一言もなく
「友ちゃん、お兄ちゃんいる?」と、きく。
「綾ちゃん、ひさしぶりー! 俊ちゃん、今、名古屋いってて明日帰ってくるんだけど、ねぇ、お父さんも、綾ちゃんも元気?」少々スローで声が大きいが、それでも以前とそれほど変わらぬ調子にほっとして、かかわりたくないと思っていた彼女に打ちあける。
「実はさ、お父さんが入院しちゃったんだよ」
「えー、どうしたの?!」
「胸が苦しいっていうから受診したら特に問題なかったんだけど、もう八十過ぎているじゃない、入院していろいろ検査してみましょうっていうことになっちゃったんだよ」
「ああ、そう。じゃあ、俊ちゃん、今日中にもどってきてもらったほうがいいかな?」
「いいよ、いいよ。今日、あわてて帰ってくることはないよ。でもね、実はさ……」
「え? どうしたの?」
「お父さん、一人で神経内科いって頭のMRIとってきてさ、今日二人で結果ききにいくつもりだったんだ。それなのに、その前に具合悪くなっちゃったでしょう。それで、私ひとりで結果ききにいったんだけど……」
「うん」
「脳幹だったかな、そこが萎縮しているらしくて、進行性の命にかかわる病気だって言われちゃったんだ」
「お父さんには話したの?」
「まだ。今、先生からきいたばかりでさ、どうしたらいいかお兄ちゃんに相談してみようと思って電話したんだ」
「そう、俊ちゃんの携帯番号知ってる?」
「携帯、家においてきちゃって、今、わからないんだ。教えてくれる? ちょっと待ってメモするから……はい、お願い」
「090-○○○○―△△△△」
「090-○○○○―△△△△だね。わかった。有り難う」
「ねぇ、私、これから病院に行くよ」
「ええー、大丈夫なの?」
「大丈夫、今、急いでやらなきゃいけないことないし。M病院だよね?」
「うん」
「そしたら、三時には着くから。病室は?」
「三〇五」
「わかった。じゃあ、後でね」
不思議なものだ。どうぞ友ちゃんが電話にでませんようにと祈っていたというのに、彼女がきてくれることになって心底ほっとしたのだから。