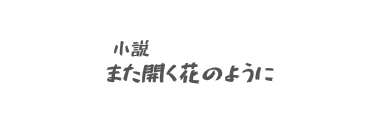父の介護認定

ふと気づけば三十八歳。このまま結婚できず、父が死んでしまったら、自分は一人で生きていけるのだろうか? 生まれてはじめて真剣にそう考え、私は青くなった。郵便局のバイト代だけでは絶対に生活できないし、それじゃあ、今からどこかに就職できるかといえば絶望的。六十五歳まで根性で生きのびたとしても、もらえる年金は月十万に遠く及ばない。
父に代わる誰かをみつけないかぎり生きてはいけない。
おまけに、「子供は持てるでしょうか?」と、思わずM女史に聞いてしまったほど母になることを夢みていたというのに、すでにタイムリミットが近づいている。
もし、父がぼけたり病気になったりして、今度は彼の面倒をみなくちゃいけなくなったら、最後のチャンスを確実に逃す。
今しかない、今ならまだ間に合う。
それでも、結婚相談所に登録するのではなく、メル友を募集したのは、どこかで、とんとんと話が進んでいくのが恐かったからのような気もするが、ともかく私は、人生のパートナーをみつけるべく行動を起こした。
だが、ひとりで舞い上がることが得意な私としては夢をみさせてもらえたが、結局うまくいかなかった。種の保存が本能なら自然なのかもしれないが、三十九歳になり一日一日と四十歳に近づきはじめると私の情緒は乱れだした。
一体、自分は、貴重な三十代に何をしていたのだろう。満足していたはずの日々に疑問を感じはじめ、後悔がよぎる。
仕事のストレスもなく好きなことをやっていたから、二十代のように、自分を助け出してくれる王子様をさがす必要がなかったというのが一番の理由なのだろうが、子供を持つことを計画してこなかったなんて言うから暗示にかけられたのだと、友ちゃんを恨んだりもした。
郵便局のバイト仲間の中心的な話題は子供の受験。
自信の無さから常に作り笑いを浮かべているような私だったが、仲間はずれにされているという思いがつのり、ある日、ぷつりと切れてしまった。
皆からあからさまに距離をとり、どんどんいやな奴になっていく。
当然、白い目で見られるようになったが、「ごめんなさい、私もお母さんになりたかったの」なんて、言えるわけがなかった。
こうして私は、なりたくなかった四十歳になった。
それでも、なってしまえばあきらめるしかないわけで、私は、子供を持たない人生を受け入れはじめ、沈み込んだところから徐々に浮上しはじめた。
けれど、子供を育てるお金はもちろんすべて人生のパートナーとなる人をあてにしていたわけで、私の一生の面倒は誰がみるのかという問題は依然未解決のまま。
四十歳まで貯金もせずに勝手なことをやってきて、今さらまじめにこつこつ働いてきた他人を頼るというのは、あまりにも虫が良すぎる。やっぱり自分で面倒みるしかないんじゃないの? ひとり、二階の自分の部屋で悶々と考えていると、ガタガタと家が揺れ出す。地震かと身構えると、ゴーッという音を立ててトラックが通り過ぎ揺れがおさまる。半永久的なものだと思っていたというのに、土台となる一階部分は昭和二十年代に建ったときのままである木造の我が家に寿命が近づいていることを知り、私はなおさら青くなった。
私が四十歳の十二月、少しでも安く一階のトイレを和式から様式に改修するため介護認定を受けたいと言い出したとき、父はすでに、将来に対する大きな不安を感じていたのだろう。
けれど、運動不足で足腰が弱っただけと思っていた私は、
「お父さんが認定されるわけないじゃない。そんなに甘くないよ」と、相手にせず、調査員が家にきた日も、いつもとかわらずバイトに出かけていた。
だから、介護認定がおりたときは驚いた。
しかし、父が、トイレの改修だけではなく風呂場に手すりをつけ、外にでかけるときは杖をつきはじめると、さすがに、不安になった。
私にとってはあまり良い思い出のない、親が死んだらおさらばしようと思っていた家でも彼にとっては違うはず。
寝たきりになった父より先に家の寿命がやってきて傾きはじめたらどうしよう……。
家の補強をするにしてもかなりのお金がかかるはず、私は彼の脛をかじりつづけてきたことを後悔した。
そして、ともかくこの低収入な生活から抜け出さねばと決意した。
自業自得で郵便局の人間関係がぎくしゃくしはじめたこともあって新しい仕事を探しはじめた。
けれど、やっぱり、なかなかうまくいかない。
ある日のこと。目を覚ましすぐにパソコンを開き仕事を探しはじめたものの、雇ってもらえそうな職場も、自分ができそうな仕事もみつけられない。一時間ほどして暗い気分で一階におりると、
「綾子、助けてくれ」という父の弱々しい声が聞こえてくるではないか。
「お父さん、どこにいるの?」と、叫ぶと、
「ここだ、ここだ」という返事が。
大きな食卓の反対側にまわると、なんと椅子の横で彼が仰向けに倒れている。
「お父さん、大丈夫?」
「ああ、椅子に座りそびれて落ちたとき腰を打ったらしくてな、どうしても一人じゃ起きあがれないんだ」
私は後ろから父の脇の下に両腕を差し込み、力づくでひきずりソファーの上に引っぱりあげて座らせた。
「病院いく?」バイトを急に休むことはできればさけたくて、乱暴な口調できく。
「大丈夫だ。ここで少し休めばすぐ良くなるさ」と、父。
結局、あの日、私はバイトに出かけ、いつものように残業をして帰り、いつもと変わらぬ父を見て、問題なしと片づけた。しかし、父自身は、足腰の衰えだけが原因ではないと感じたのだろう。
あの出来事から数日後、バイトから帰った私は、神経内科を受診し頭のMRIをとってきたときかされ驚いた。
「ええ~、どうして頭なの? それで、何か言われたの?」
「いや、結果は一週間後なんだ」
父もまた軽い脳梗塞を起こし床に倒れたというのか? 心配になった私は、一緒に結果をききにいくため、はじめて彼のため休みをとった。
だが、心を入れ替え、彼を大切にしようなんて全く思わなかった。
仕事を探しはじめて早三ヶ月。ここでくじければ未来はないと私はひたすらあせっていた。