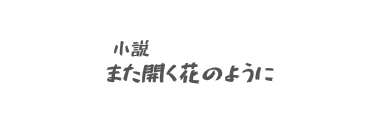こぼれ落ちる愛

「父さん、染野さんの大事な娘をあずかったつもりでいるから、友のことだと、俺のことなんかよりずっと大騒ぎになっちゃうんだよな。でも、嘘ついていられないし、自分からもう一度電話いれておくよ」
別れ際に言っていたとおり、兄は、私が帰りつくまえに、電話で父と話をしていた。
「友ちゃん、大変な事故だったんだってな」という父が、意外と落ち着いていたのは有難かったが、兄と同じく、意識がもどったことに感謝して後遺症のことはほとんど心配していない様子。
車で迎えにいくから、それまで風邪を治すよう兄から言われた一週間後を彼は心待ちしていたが、私には、それも辛かった。
どこかで見たことがある。そう感じた友ちゃんのあの目。あの目に象徴される頭の病を、私は自分がかかる以前から嫌い恐れていた。そして、経験してしまったことで、頭がいかに繊細で、一度バランスをくずしてしまうとどれほど厄介かということを思い知らされてしまった。
友ちゃんの意識がもどり絶望から救われた兄には、まだ、彼女の異様な行動も異様とはうつっていない。けれど、一週間経てば、彼女が負った障害の大きさを無視することはできなくなる。そして、もう若くない父も、私たちと同じく自分の子供のようにかわいがってきた彼女の変化にどれほどのショックを受けることだろう。
私にとって血のつながりは特別で、子供の頃から父母や兄の痛みと自分の痛みをわけることが難しかった。
しかし、義姉であるとはいえ常に一線を引いてきたはずの友ちゃんのためにとめどなく涙がこぼれてくるのには自分自身も驚いた。
夜、父から逃げるように二階に上がりベッドの上に転がると、私を呼ぶ友ちゃんの姿が次から次へと頭に浮かんでくる。
「アーヤーちゃん」
「あやちゃーん」
「綾ちゃん」
子供の友ちゃん、大人の友ちゃん、元気いっぱいの友ちゃん、蝶のようにきれいになった友ちゃん。
私と違って、友ちゃんの思考はいつものびやかで、事故にあわなければ頭の病には、まずならなかっただろうに。
「友ちゃん」と、声に出して呼んでみると、彼女は寝間着姿となり、白い壁の長い廊下を首を傾げたままゆっくりと遠ざかっていく。私には、三十九歳の彼女が、病院という場所から出られるとも思えなくて、悔しくて悲しくて、涙がぽろぽろとこぼれた。
どれぐらい、時間が経ったことだろう。
ベッドの上に正座して、むせび泣きを続ける自分を、もう一人の自分が静かに眺めていた。
私はこんなにも友ちゃんのことを愛していた……。
胸のあたりからこんこんと湧き上がり、すすり泣く声とともに、かすかなきらめきを放ちながら溢れ出し、自分の手の上に落ちていく何か。
もう一人の自分とともに、私は静かにそれをながめていた。
もし、兄の運転する車で父と春子おばさんと一緒に再び病院にいったあの日、友ちゃんが見るからに普通ではない状態だったなら、私は間違いなく地獄を味わうことになっていただろう。
けれど、もう少し歳を取り図太くなるまで猶予があたえられ、ベッドの上で私たちを待ち構えていた友ちゃんは、
「心配かけちゃってごめんなさい。あら、春子おばさんも来てくださったの。本当に有り難うございます」と、実に、はきはきとあいさつしてくれた。
肉体から抜け出し、もう戻ってこないかもしれないと思っていた彼女が確かにそこにいたのだもの。うれしくて、うれしくて、あれ? と、思うべきことも気づかぬふりをしてしまった。
車で我が家まで送ってくれた兄が病院に引き返すと、私たちは熱いお茶を入れ、春子おばさんが持ってきてくれた和菓子を食べた。
「友ちゃんの元気な顔がみれてよかった」と、父。
「うん」と、私。
「私なんて、友ちゃんが大変な事故にあったってきいちゃったもんだから心配したわー」と、父より先に画廊を経営する知人から話をきいたという春子おばさん。
「タクシーの運転手さんは、かなりひどい怪我をしたようだし、嘘じゃないさ。本当によかった」と、父。
「うん」と、私。
「でも、友ちゃん、ずっとしゃべりつづけていたわね」しばしの沈黙。それから、春子、おまえに言われたらかわいそうだよとは言わず、父が、
「ああ」と、同意した。兄が医者から言われた後遺症という言葉も杞憂だったのだと払いのけたというのに、再び、じわりじわりと不安が広がって、私は「あはは」と、ひきつりながら笑った。
その後、私たちが病院にいくことはなく、九月に入るとすぐに友ちゃんは退院し、兄と二人の生活に戻っていった。
彼女はもう病院という場所から出られないのではないかと憂い職場でさえ涙したことを思えば、奇跡といっていいような展開。
けれど、例のあの目と、春子おばさんが言ったとおり確かにしゃべりつづけていた友ちゃんが気にかかり、兄夫婦にはあまり深く関わらずにおこうと一人ぺろりと舌を出した。
どうかすべてが元に戻りますように、その願いを込めたぺろりだったが、振り返るとその後の三年ちかく、私は、深く関わらないどころか、兄夫婦に起きていることを知ろうとさえしなかった。
退院した年だったか一度だけ、二人そろって我が家に顔を出したことがあったが、特に強い違和を感じた記憶はない。
けれど、事故は確実に友ちゃんの頭にダメージをあたえていて、奇跡と思えた退院も、手放しで喜べるものではなかったことを後から知った。
彼女の元気が度を越しているのは医者や看護師からみれば一目瞭然。目を覚まし、なぜこんなところで一人寝ているのか事情がわからず、お母さんやお父さんをさがして病院中を歩きまわり、その間、病棟では大騒ぎなどということも何度かあったという。
それでも、頭の検査によって損傷を受けている箇所が明らかになったわけではなく、安定剤や睡眠導入剤を処方されるだけの入院生活を送るうちに、家に帰り再び筆を握ることが最良の薬ではないかと二人が思ったのにもうなずける。
しかし、誰もが願うようにすんなり元に戻ることはなかった。
事故後の経過とあの日、友ちゃんに会った印象から、ことの深刻さをすでに受け入れていた父は、まめに兄と電話で連絡をとりほとんどのことを把握していたようだが、年老いた彼を心配していたはずの私はといえば、相談相手にならぬどころか、何も聞きたくないという強烈なオーラを発していたのだろう。
「右手のしびれがとれないようで、友ちゃんがリハビリのため入院したそうだ」と、聞いたのは一度だけではなかったが、父としては、私がもっとも傷つかない理由だけを選んでくれたにちがいない。
夜、寝ないで筆を握りつづけ、明け方、兄がアトリエをのぞきにいくとカンバスを飛び出し壁にまで絵を描いていたというから、入院の一番の理由は、やはり右手のしびれではなかったのだろう。
「これじゃあ、俊ちゃんが人形作りに集中できないし、私も疲れてきちゃったから、もう一回、病院いって休んでくる」と、友ちゃんから言い出したということをやはり後から知った。
愛するふたりが事故のために離れ離れにならなくてはいけないなんて何という悲劇。話を聞いたときは涙が出そうだったが、有り難いことに、実際は、それほど暗くもなかったようだ。
あれも後遺症のひとつだったのかもしれないが、事故後、友ちゃんの思考はさらにポジティブになり、医療機関で働く知人の紹介で入った病院のことも気に入っていたというのだ。
特別ひどいところを紹介していたのだろうが、いつだったか図書館で見てしまった院内の写真があまりにも暗くて不衛生だったこともあって、父の口から精神病院という言葉が出てくるのが恐くて、何も聞きたくないという態度をとりつづけた私は、彼女が入った病院がどんなところだったのか今もしらない。
しかし、筆を持つ右手のしびれのせいだけではないと思うが、事故後、以前のような絵を全く描けなくなった彼女は、創作にいきづまると、保養所にでも出かけるように簡単な画材を持って病院に入り、そのたびに作風が確立していったという兄の話からしても、普通の病院ではなかったのだろう。
何はともあれ、最後に退院したとき、彼女は、
もう、あそこに行く必要はないから、ずっと一緒にいようね」と、言い、それを聞いた兄は心底うれしかったというから、それなりの苦労があったのは間違いない。
おそらく、彼女の言葉を電話で聞き、兄と喜びあったのだろう父も、見舞いに行かず、そんな時がくるのを待ちつづけていたのだろう。だが、加齢と心配で小さくなった彼の背中を見て、ようやく、一生、脛をかじりつづけることはできないと気づいた私はといえば、やはり自分のことばかり考えていた。